
モノ
2022.04.28 THU.
和歌山の老舗ニッター「カネマサ莫大小」が生み出す、
至極のニットとモノづくりの礎。
日本最大シェアを誇る丸編みニットの産地・和歌山。古くは明治42年にスイス製の丸編み機を導入したのがはじまりといわれます。ソフトな風合いが特徴の生地・別名メリヤス。〈ユナイテッドアローズ(以下、UA)〉と〈ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ(以下、BY)〉でも、そのハイクオリティなファブリックに注目し、取り組みを続けてきました。和歌山のニッターの中では後発組でありながらも、いち早くハイゲージに特化した特注のジャカードマシーンを取り入れ、いまでは“ハイゲージといえばカネマサ”と言われるまでになった「カネマサ莫大小株式会社」取締役の百間谷 浩平さん、企画営業の佐野 新季さんのおふたりに、そのモノづくりの背景やファクトリーブランドについて、また、これからのメリヤス産業に対する想いまでを語っていただきました。
Photo:Shunya Arai(Yard)
Text:Akiko Maeda
丸編みニットの一大産地・和歌山での
〈カネマサメリヤス〉のモノづくりの歴史。

一まず、おふたりの経歴を教えてください。
百間谷:僕は「カネマサメリヤス株式会社」の三代目という立場になりまして、現社長が僕の父にあたります。といっても、すぐに家業を継いだというわけではなくて、大学を卒業後に名古屋の繊維商社で3年間糸売り、生機売りなどを中心に経験を積みました。
一百間谷さんが家業に戻られたきっかけは何だったのでしょうか?
百間谷:あるとき、家業の様子が気になって少し父と話したときに、素晴らしい機械を持っていてモノを作る精神はすごくあるけれど、それを売る力が足りていないと感じたんです。この素晴らしい生地をもっと多くの企業に知ってもらうこと、また、アパレルの会社さんと組んで商品を作ることもできるのではと思い、父に「戻らせてほしい」と話をしたのがきっかけです。

佐野:僕は大学卒業後、いわゆる「付属屋」と呼ばれる、服の表地以外のものを作るアパレル商社に就職したのがアパレル業界に入ったきっかけです。実はそのときからいまの会社ともお付き合いがあって、取締役と同世代ということもあって交流させてもらっていて。「自分でブランドを立ち上げたり、新しいことをやりたいんだ」と相談していて、それならということで、2020年の9月に入社しました。
一もともとお付き合いがあって、いま一緒にお仕事をされているなんて運命的ですね。
編み機、糸、職人の技術まで。
すべてが「カネマサ」オリジナル。

一「カネマサメリヤス株式会社」のはじまりについて教えてください。
百間谷:1900年代初頭にスイス製の丸編み機が入ってきたことをきっかけにはじまった和歌山のメリヤス産業ですが、弊社は1964年創業と和歌山のニッターの中では後発組の会社になります。元々大量生産型のニッターではなくて、「〈カネマサメリヤス〉にしかできない生地を作る」というフィロソフィーを持って祖父が創業しました。そこから、編み機を改造して職人自ら機械をまわしてウチにしかないオリジナルの生地を一から作ってきました。
一他にはないものを追求するという“差別化”の精神が素晴らしいですね。
百間谷:その後、現社長である父が事業を受け継いだ後も、その点は変わらず根付いている精神ですね。理系だった祖父とは真逆でバリバリの商社マンだった父が機械の別注をはじめたんです。
百間谷:その当時どこにもなかった、36Gという高密度のジャカード生地が編める機械を日本ではじめて導入したことで、「ハイゲージニッター」としての歴史がスタートしました。いまでは当たり前になっている、布帛調のニットシャツやジャケットパンツに関してはウチがパイオニアといえると思います。

編み機のイメージをくつがえす近未来的なルックスの最新スーパーハイゲージマシン。もちろん、最新の機械を導入すれば高品質な生地が作れるというわけではなく、このマシンを扱うことができる職人の腕があってこそ。いまでは46Gの生地までを編むことができるそう。
一では、こちらで行われている主な作業はどんな工程があるのでしょうか?
百間谷:「糸を仕入れて、マシンを使って生地を編み立てる」というのが主な作業になります。また、弊社では糸の別注を行っているのも大きな特徴です。何十トンという単位、服でいうと何百万枚という単位で別注するのが一般的です。正直、この規模のニッターで糸の別注をしている会社はなかなかないのではないかなと思います。

一そんな膨大な単位で別注されるとは驚きです。では百間谷さんが考えるいい糸とはどのような糸でしょうか?
百間谷:父も僕も商社出身なのでこれまでに養ってきた知見を生かして地道にいい糸を探していますが、いまでいうと高品質でサステナブルな糸ですね。自社開発した「スピンリサイクルオーガニック」という糸は、コットンでありながらまるでシルクのような繊細で上質な肌触りが特徴です。
一サステナビリティが叫ばれる現在の市場のニーズともマッチしていますね。環境に配慮したモノづくりは会社としていつ頃から意識されていたのでしょうか?
百間谷:十数年前から世界最高峰の服地見本市である「プルミエール・ビジョン」に出店させていただいているのですが、ヨーロッパでのサステナビリティへの関心はどこよりも高かったですね。我々も比較的早い段階から環境を配慮する姿勢を持ってきたつもりです。

現在も現役で活躍する、旧式のヴィンテージ編み機。ゆっくりと時間を掛けて編むことでやわらかな風合いのある生地に仕上がる。
ファクトリーブランド「KANEMASA」
だからできること。

一昨年スタートされたファクトリーブランドも、先ほどお話に出た自社開発糸「スビンリサイクルオーガニック」を使用しているそうですが、D to Cブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。
百間谷:ひとつは「適正なプライスで適正な価値を持った商品を届けたい」ということ、もうひとつは「本当にいい生地をお客さまに知ってほしい」と考えたからです。いままでOEMに徹していたことで、いくら我々が“この生地は素晴らしい生地だ”と思ってもお取引先さまであるアパレル会社さんが選んでくれなければ世に出ることはないんです。そこにもどかしさを感じたのがきっかけです。

佐野:自社ブランドを立ち上げるタイミングで僕が入社したのですが、スタートは2020年11月に行った「Makuake」でのクラウドファンディングプロジェクトでした。36Gのスーパーハイゲージスウェットのテストマーケティングが目的だったのですが、ブランドのターゲティングからビジュアルの制作、製品の形や色決めまでを入社したばかりの僕に一任してくれたんです。
百間谷:クラウドファンディングのサイトの写真や原稿も佐野が中心となって手掛けました。
佐野:すごく良い経験になりましたね。会社にとっても僕自身にとっても、クラウドファンディング自体は初めての試みで最初はどうなるのかと不安でしたが、おかげさまで900万円以上の資金調達を達成し、お客さまからもご好評いただきました。
百間谷:クラウドファンディングの期限当日にふたりで達成金額に一喜一憂しながら鍋を囲んだのもいい思い出ですね(笑)。
佐野:もちろんブランドを立ち上げるのも初めてでしたし、こんなに大変なんだ…と難しさを感じた瞬間も多々ありましたが、僕にとっては人生としての岐路となったといっても過言でないくらいの達成感でした。そして「Makuake」の後、Caravel.LLCの馬場さんにディレクションをお願いし、ディレクターとして今の形になりました。
一なかなかできない経験ですよね。では、ブランドを立ち上げる上でこだわった点はどんなところでしょうか?
百間谷:「KANEMASA」は、「このアイテムを作るなら、どんな生地が適しているのか」ではなく、あくまでも「この生地でなにができるか」という生地先行型のモノづくりです。世の中にファクトリーブランドが乱立する中でどう差別化するかという点でしょうか。一見するとファクトリーブランドには見えないけれど、「どんな生地を使っているんだろう?」と興味を持ってくださった方が調べてみたら、“実は老舗ニッターのファクトリーブランドだった”というのが理想ですね。
自慢の生地を使い新たな商品を世に。
UA社との取り組み。

一続いてUA社との取り組みについて聞かせてください。協業することになったきっかけは何だったのでしょうか?
佐野:これまで〈BY〉さんなどで、別注商品を発売しておりましたが、ブランドとしての協業は、2021年7月開催の「WHAT’S KNIT?展 -これが、ニット。これも、ニット。」の際に、Caravel.LLCの馬場さんと親交があった〈ユナイテッドアローズ&サンズ〉のディレクターである増田 晋作さんに来ていただき、ローンチしたばかりのコレクションを見ていただいたことです。
そのときにサンプルをお見せしたソラーロの生地を増田さんがUAメンズのファッションディレクター内山さんに伝えてくれて、それをすごく気に入ってくださいました。
「この生地をメインになにか一緒にモノづくりをできないか」というところから「KANEMASA」との協業のお話がスタートし、AWコレクションでは、UAさんが得意とするテーラードを楽に着られる素材で作るということに挑戦しました。内山さんのイメージしているデザインに対して、馬場さんと僕とで形から色を提案し、細かな部分まで打ち合わせを重ねて作り上げました。
百間谷:我々のモノづくり目線とUAさんのファッション的なアプローチが融合することで新たな商品が完成したことが、すごく嬉しいです。

〈BY〉との別注スウェット。世界的にも希少な特注編み機を使って編み上げられた、「カネマサメリヤス」の真骨頂であるスーパーファインゲージファブリックを贅沢に使用している。
高品質な技術やモノづくりの哲学を
若い世代が中心となって伝えたい。

一今後、どのようにメリヤス産業を広めていきたいですか?
それぞれのニッターさんがそれぞれ個性を持っているのが特徴の和歌山の産地では、各社が違うベクトルから地場産業を盛り上げていけるのが強みではないでしょうか。弊社は海外にはないオンリーワンの生地を作ることができるという強みを生かして、海外への輸出に注力していきたいと考えています。
一まさに世界へ向けてのビジョンですね。また、モノづくりの現場において常に課題となる後継者問題についてはどうでしょうか?
百間谷:後継者問題については、我々にとっても他人事ではありません。「カネマサメリヤス」では、社員全員が正社員雇用で、地元の人を積極的に採用することで、地域の持続可能性を目指し、ひいては地場産業を守ることに繋がるのではないかと考えています。

高齢化が進むモノづくりの産地では珍しく、若手の社員の姿が目立つ工場内。若いパワーで地元の産業を盛り上げている。
佐野:あとは、僕たちのような20代という若い世代が自社ブランド「KANEMASA」のイニシアチブをとってどこもやっていない新しいことを実現することで、地場産業を盛り上げていきたいです。納得できるいい商品を作るのはもちろんのことですが、若い世代ならではのフットワークの軽さを生かしてポップアップを積極的に行って、僕がお客さまに直接商品の魅力をお伝えする場を持つことも大切にしています
百間谷: 最近では僕らよりも若い方々がモノづくりの裏側に興味を持たれて、実際に弊社の工場に見学に来てくれたこともあります。ニッターの地位向上というと大げさかもしれませんが、僕たち自ら誇りを持ってこの仕事に向き合う姿を後の世代に見せていくことも、地場産業のさらなる発展に向けてのひとつのきっかけになるのではないかと思っています。

INFORMATION
PROFILE
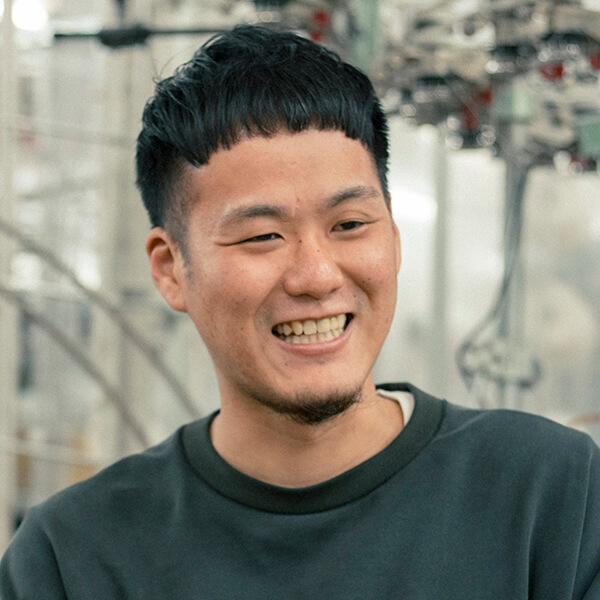
佐野 新季
1994年1月24日生まれ。大阪府出身。2020年カネマサ莫大小株式会社に入社。ブランド事業部担当。











